売却
- HOME
- 売却
売却の流れ

1.ご相談・査定
不動産会社に相談し、周辺相場や物件の特徴をもとに査定を受けます。

2.媒介契約の締結
売却活動を依頼するために、不動産会社と契約を結びます。

3.売却活動
広告掲載や内見対応などを通じて、購入希望者を探します。

4.売買契約の締結
条件交渉を行い、合意に至れば売買契約を結び、手付金を受領します。

5.残代金の受領・物件引渡し
残代金を受け取り、登記や鍵の引き渡しを行い、売却が完了します。
査定方法

1. 取引事例比較法
実際にその地域で「どのくらいの値段で売れたか」を参考にして査定する方法です。 たとえば、周辺のマンションや一戸建ての過去の売買価格と比べて、「駅からの距離」「築年数」「広さ」などを調整して価格を出します。

2. 原価法
もし今その建物を建て直したら「いくらかかるか」をもとにして価格を出す方法です。 ただし築年数や劣化を考慮して、建物の価値を調整します。

3. 収益還元法
「この物件を貸したらどのくらいの収益が見込めるか」を基準にして価格を算出する方法です。 賃料収入や利回りから逆算して、物件の価値を判断します。
必要書類
| 書類名 | 一戸建て | マンション | 土地 |
|---|---|---|---|
| 登記済証(権利証)または登記識別情報 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 本人確認書類 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 物件の間取り図 | ◯ | ◯ | × |
| 確認申請書、検査済証 | ◯ | × | × |
| 固定資産税納税通知書 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 実印・印鑑証明書 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 固定資産評価証明書 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 住民票 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 土地測量図・境界確認書 | ◯ | × | ◯ |
| 管理規約など(マンションの場合) | × | ◯ | × |
相続の流れ

1.相続開始・相続人の確認
被相続人が亡くなると相続が開始します。まず戸籍を確認し、誰が法定相続人になるのかを確定します。
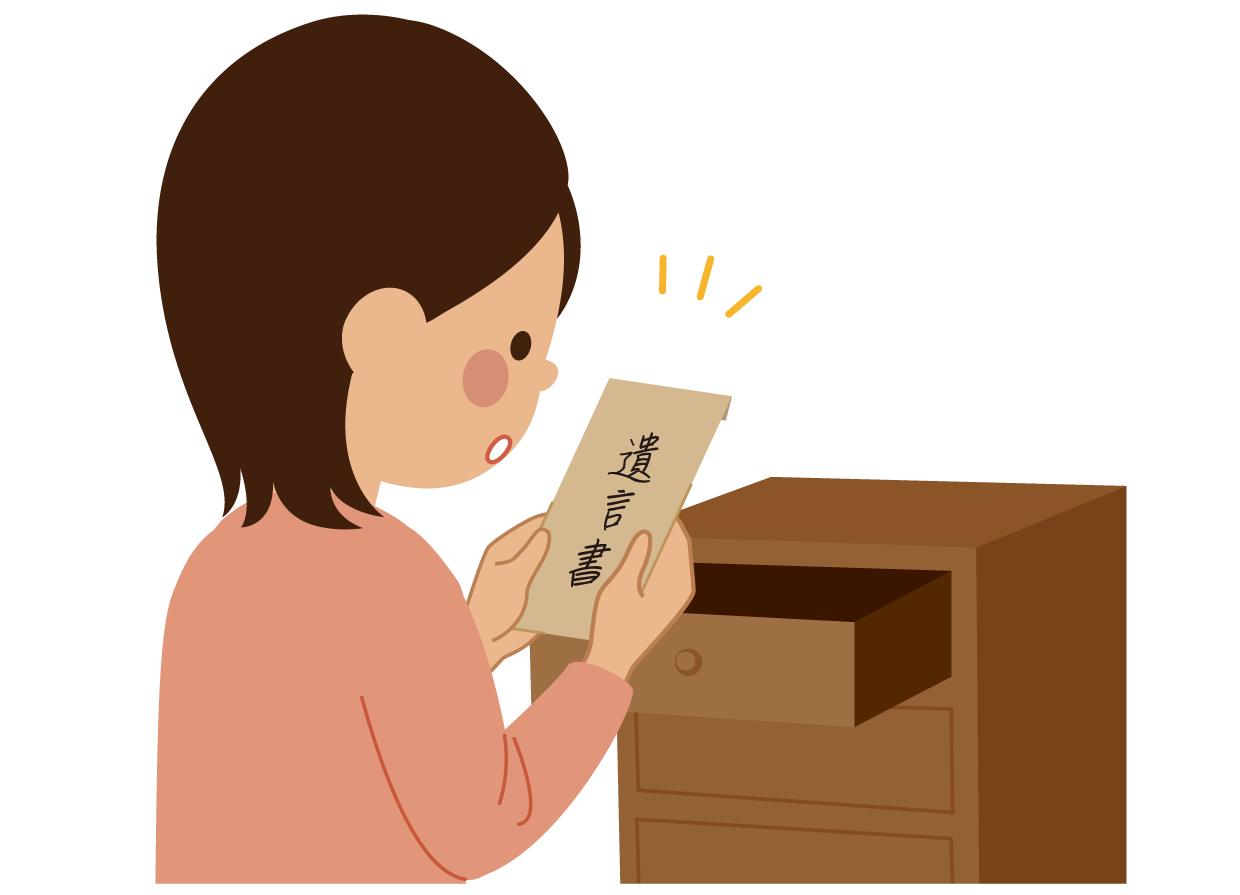
2.遺言書の有無を確認
公正証書遺言や自筆証書遺言など、遺言書があるかどうかを確認します。
遺言書があれば、その内容に沿って進めます。

3.不動産を含む財産の調査
土地・建物の登記簿や評価証明書を取得し、不動産の種類や評価額を把握します。併せて預貯金や負債など全体の財産を整理します。

4.遺産分割協議
相続人全員で、不動産を「誰が相続するのか」「どのように分けるのか」を話し合います。共有にする場合や売却して現金で分ける場合もあります。
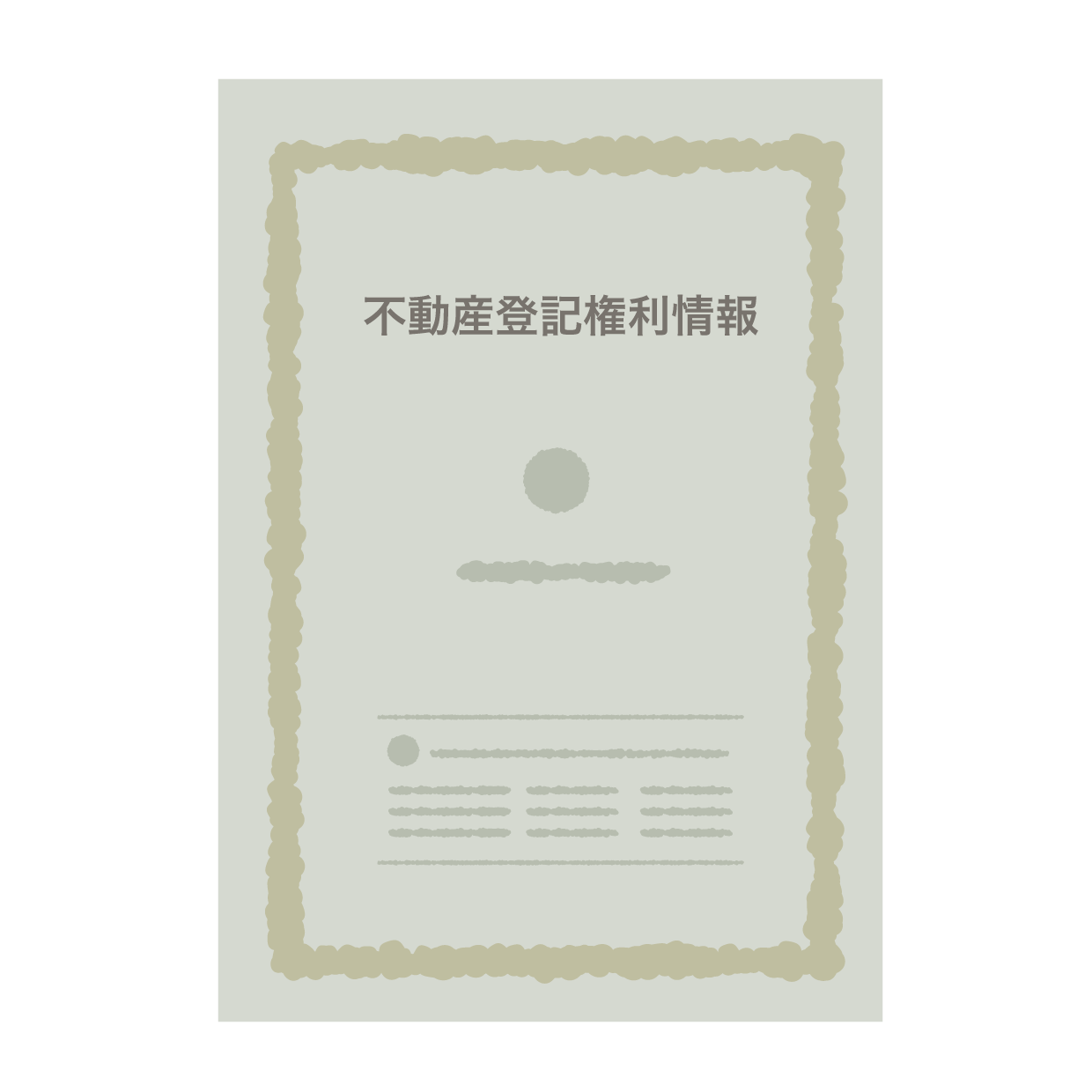
5.相続登記(名義変更)
不動産を相続する人が決まったら、法務局で名義変更を行います。2024年4月からは相続登記が義務化されているため、手続きを忘れると過料が発生する可能性があります。

6.相続税の申告・納付
課税対象となる場合は、相続開始から10か月以内に相続税の申告・納付を行います。
不動産の評価額が大きいと税額に影響するため、早めの確認が大切です。
相続のデメリット
借金や債務も引き継ぐリスク
単純承認を選ぶと、プラスの財産だけでなく借金・未払い金などマイナス財産も相続します。
財産状況を確認せずに承認すると、予想外の債務を負担することになります。
相続放棄のデメリット
相続放棄をすると、プラスの財産や思い出の品、不動産も受け取れなくなります。
一度放棄が受理されると原則撤回できず、次順位の 親族に相続権が移り、親族間トラブルに発展する可能性もあります。
限定承認のデメリット
相続人全員の同意が必要で、手続きが複雑です。
専門家への依頼や手続き費用がかかり、時間とコストの負担が大きくなります 。
固定資産・不動産の負担
不動産を相続すると、活用していなくても固定資産税や維持管理費用が発生します。
空き家のまま放置すれば、特定空家に指定され固定資産税が増える可能性もあります。
相続税の負担
一定額を超える遺産には相続税が課税され、多額の税金が発生することがあります。
特に不動産は評価額が高くなりやすいため注意が必要です。
相続手続きの複雑さ・期限
相続放棄や限定承認には「相続開始から3か月以内」など期限があり、対応が遅れると選択肢が狭まります。また、遺産分割協議では意見がまとまらず、親族間トラブルに発展するリスクもあります。
税金のデメリット
相続税の負担が大きい
不動産は評価額が高くなりやすいため、遺産総額が基礎控除額を超えると多額の相続税が発生する可能性があります。
特に都市部の土地やマンションは評価額が高くなり、現金で納税できず困るケースがあります。
現金化が難しく納税資金に困る
相続税は原則「現金」で納める必要があります。しかし不動産はすぐに売却できないため、
相続人が自分の貯金を切り崩したり、物件を急いで安値で売却せざるを得ない場合もあります。
固定資産税などの維持費が発生
相続後は相続税に加えて、毎年の固定資産税や都市計画税がかかります。
活用していない空き家や土地でも所有しているだけで税金がかかるため、長期的な負担になりやすいです。
小規模宅地等の特例が使えない場合がある
自宅や事業用の土地には相続税を大幅に減額できる「小規模宅地等の特例」がありますが、相続人の居住要件や利用実態など条件を満たさないと適用できません。
条件を満たさずに税負担が重くなるケースもあります。
相続税以外にも税金がかかるケース
不動産を相続後に売却する場合、譲渡所得税や住民税が発生します。
さらに短期間で売却すると税率が高くなるため、想定外の負担になることがあります。
空き家のリスク
犯罪の標的になりやすい
人が住んでいないことで「狙いやすい家」と見られ、
特に夜間や人通りの少ない場所では標的になる可能性が 高まります。
放火されやすい環境の存在
庭や敷地に雑草、廃材、ゴミなどの可燃物があると、火をつけやすい環境を自ら提供してしまいます。
施錠・防犯対策の不備
玄関や窓の鍵の不備、壊れたフェンスや放置された窓ガラスなどは、侵入や放火のリスクを大幅に上げます
火災発見の遅延と被害拡大
無人のため発見が遅れやすく、近隣住宅に延焼して損害が大きくなることもあります。
その場合、所有者が損害賠償責任を問われるリスクもあります。
タバコのポイ捨てなどによる火災
空き地に放置されたゴミや可燃物が、通行人のタバコの火種などで発火するケースもあります。
所有者責任の発生
管理が不十分と判断されると、火災で近隣に被害が及んだ場合に所有者が責任を負うことになります。
空き家対策
定期的な管理・巡回
換気・清掃・庭木の手入れ・老朽化チェック・ポスト回収を行い、管理されている印象を与えることが防犯の基本です。
遠方なら「空き家管理サービス」を利用するのが有効です。
防犯カメラ・監視カメラの設置
設置するだけで抑止効果があり、万一の侵入時も証拠になります。
夜間や人通りの少ない場所では特に有効です。
防犯グッズの活用
窓ガラスに防犯フィルムを貼る、補助錠や防犯ブザーを設置することで、
侵入に時間がかかり犯行を諦めさせやすくなります。
センサーライトや防犯砂利の設置
人の動きを感知して点灯するライトや、踏むと音が出る砂利を使うことで、不審者の心理にプレッシャーを与えます。
防犯ステッカーや標識
「防犯カメラ作動中」「管理会社巡回中」といった掲示を出すだけでも大きな抑止力となります。
空き家管理サービスの活用
専門業者が定期巡回・換気・清掃・ポスト回収を代行してくれるため、遠方に住んでいる方や多忙な方でも安心です。
郵便受け・ポストの処理
郵便物やチラシが溜まると「空き家」と一目でわかってしまいます。郵便の転送や定期回収を徹底しましょう。
